
大学院医療科学研究科 総合リハビリテーション学専攻
「いのちをまなぶキャンパス」を統一イメージとする本学では、健康を三つの段階で保障・推進することが重要であると考えています。
第一段階としては「生きる」というレベルで健康を享受すること。これは、まさに人間が生物として生きる最低限の保障です。第二段階では、健常な人間が疾病に罹患、あるいは外傷を負った場合でも、日常生活で必要な「寝る、起きる、食べる、働く」などの行為が行えるよう適切に対処され、再び普通の生活に戻ることのできる「医療」の保障があること(この第二段階は学部教育で現在、進めています)。
そして第三段階は第一、第二段階が保障された条件の下で、「自立した生活を支援すること」の推進です。このことは可能な限りの疾病の予防、健康の保持・増進をはかり、自らの生き方を考えることができる余裕のある生活、すなわち「QOL(Quality of Life)の向上」を求めるものです。急速に進む高齢化は医療・介護の社会的負担を招くことから、医療費の削減に直接的につながる「健康であること」への関心は必然的に高まっています。
このことから、本学大学院医療科学研究科 総合リハビリテーション学専攻では、本学が考える「健康の第三段階」に対応する教育・研究内容を、より広範かつ生活レベルの視点から実践できる高度専門職業人の養成を以下の三つのポリシーを持って展開します。
- 1)各分野で指導的・中心的役割を果たすとともに、他職種との適切な連携ができ、臨床・教育・研究に寄与できる高度専門的職業人の育成を目指して、体系的かつ実践的な教育を行う。
- 2)幅広い学修が可能となるよう、学際領域を含む科目を開講し、履修選択を広げて、各人の希望に応じた多様な科目を履修可能な教育課程とする。
- 3)研究科専攻において、研究のために必要な基本的事項の学修に基づき、特別研究、論文作成をとおして、批判力、論理性、表現力を育成するための教育体制を整備する。
「人間にとって必要な健康のあり方」、すなわち「疾病予防、健康増進、自立生活支援」の推進に寄与することになる教育・研究を準備して、皆さんをお待ちしています。
概要
| 設置キャンパス | 千住キャンパス(足立区千住桜木2-2-1) |
|---|---|
| 研究科名 | 医療科学研究科 |
| 専攻名 | 総合リハビリテーション学専攻 |
| 学位 | 修士(リハビリテーション学) |
| 定員 | 3名 |
受験生の受け入れ
医療科学研究科 総合リハビリテーション学専攻は、進む高齢社会にあって「人間にとって必要な健康のあり方」を学究する高度職業人を養成します。
すでに臨床現場に従事し、専門職者として更なるレベルアップを図りたいと希望を持つ社会人に門戸を開くため、大学院設置基準第2条の2に基づく教育方法を導入します。
本研究科で展開される領域には、理学療法士をはじめ医療専門資格を有する方の他に、それらの資格を有しないが地域のリハビリテーションに関心を持ち、活躍を希望している方の入学も期待しています。
大学院入学者受入方針
医療科学研究科では、様々な課題について具体的な問題意識とそれを解決するための熱意を持ち、生命倫理・医療倫理を尊重しながら、研究とその実績に取り組む積極性と行動力を備える次のような人材を求めます。
- 1)疾病の予防や健康推進、生活の支援など、地域での自立生活や社会参加の支援等に至る様々な展開に貢献しようという意欲を持った人
- 2)医療及び地域での実践場面における問題発見能力や問題解決能力をはじめ、実践研究の計画、情報処理、ディスカッション、プレゼンテーション等の能力を高め、高度専門職業人並びに実践研究者としての資質を高めたいという姿勢と熱意を持った人
- 3)高い倫理観と豊かな人間性を持った人
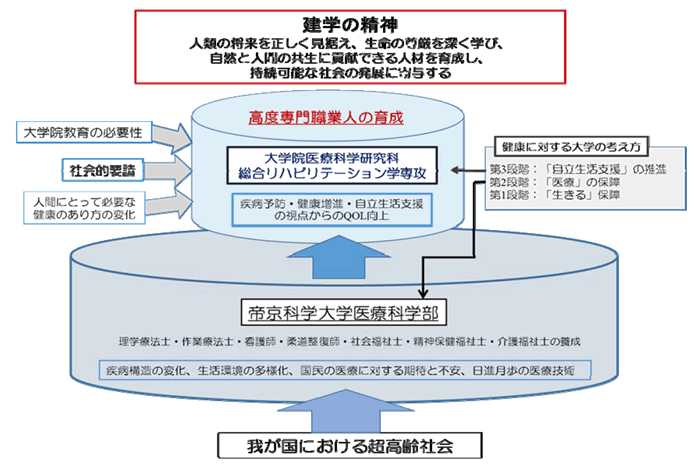
- *本計画の内容は予定であり、変更する場合があります。
研究
総合リハビリテーション学専攻では、「疾病予防、健康増進、自立生活支援」の推進に寄与できる、多角的視点から実践できる研究をめざしています。具体的な研究課題は下記のとおりです。
- 地域在住の障がい者や高齢者を対象とした体力に関連する身体機能評価(バランスや筋力、等)とトレーニング方法の開発
- 脳卒中患者に対する基本動作を中心とした課題指向型トレーニングの効果判定
- 臥位における運動負荷時の呼吸・循環応答に関する研究
- 体幹機能評価とトレーニング方法の開発
- 超高齢化する日常生活圏域の実態およびセーフティネット構築における研究
- 転倒予防および転倒要因に関する研究
指導教員及び指導内容
| 分野 | 指導教員 | 研究指導内容 |
|---|---|---|
| 医学的リハビリテーション/社会的リハビリテーション | 鈴木 幹夫 | 精神障害(気分障害、統合失調症など)についての、臨床精神病理学的研究。 |
| 山田 健司 | 人口変容による地域生活問題とターミナルケアに対応する医療・福祉セーフティーネットワーク構築およびシステムのDX化方法についての研究。 | |
| 津田 彰 | ウェルビーイング(well-being)―持続可能で多面的な幸せの状態と特性―のストレス及び健康-病気の結果に及ぼす効果に関する生物心理社会学的メカニズムの研究と実践。 | |
| 萩原 宏毅 | 骨格筋萎縮のメカニズムの解明と改善のための介入方法の開発。運動が筋・代謝・脳機能に与える影響の研究。新規理学療法的介入と評価方法の開発。 | |
| 藤田 博暁 | 予防理学療法としてのロコモティブシンドロームや骨粗鬆症に関する研究 | |
| 楠永 敏惠 | 病いや障害とともに生きる人の経験について当事者の立場から明らかにし、必要な支援を検討する研究や、在宅の医療的ケアに関する研究など。 | |
| 西條 富美代 | 福祉用具利用のメリット・デメリットを明らかにし、生活パターンに合わせた福祉用具の利用方法や介護者の身体的負担軽減方法に関する研究。 | |
| 廣瀬 昇 | 運動時の呼吸循環応答に関する基礎・臨床応用に関する研究、運動が骨格筋及び身体活動に及ぼす影響に関する研究。 | |
| 芹田 透 | 肩甲骨周囲筋に分布する血管の走行に関する研究。肩関節インナーマッスルの形態的特徴についての研究。深層筋の効果的な触察方法についての研究。 | |
| 三木 良子 | ・ソーシャルワークを基盤とした精神障害者の就労や雇用に関する研究 ・刑事事件に関与した障害者等への支援に関する研究 |
|
| 田中 和哉 | 直立二足姿勢での立位姿勢・歩行動作の制御に関するバイオメカニクス分野の研究。 立位姿勢・歩行動作における体幹運動の分節的制御に関する研究。 |
|
| 平賀 篤 | ・物理療法と運動療法の併用が身体に及ぼす影響に関する研究 ・新規運動における運動学習効果を高める方法論に関する研究 |
※指導教員については、退職等により変更になる場合があります。



