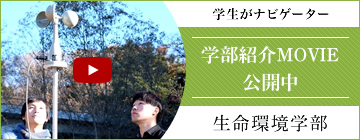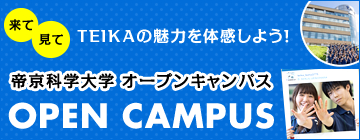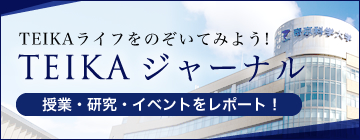Department ofNatural & Environmental Science
自然環境学科
(東京西キャンパス・千住キャンパス)
自然に囲まれた環境で、環境問題を考える視点を養う
フィールドワークを通して動植物や自然に精通する「生物環境」分野、それらを取り巻く環境問題を知り 解決策を実践する「環境保全」分野、さらにそれらを科学的に測定・分析する力を培う「環境科学」分野。 これら3つをバランス良く学べるのが本学科の特長です。 4年次からは、興味・関心に応じた研究室に配属され、専門性を深めます。 動植物に精通し、さまざまな環境問題の解決や持続可能な社会の構築について考え、実践できる力を養います。

3つの特色 Features
Point 1
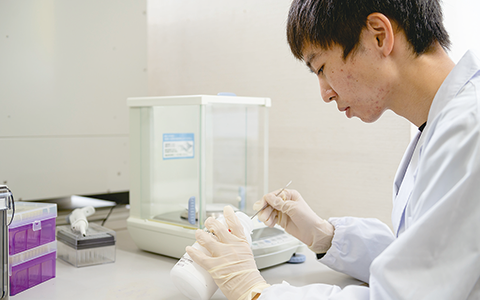
「生物環境」「環境保全」「環境科学」3方向の総合的な力を養う
環境問題を解決するために生物と自然に精通し、自然を修復するための実践的な保全技術、自然にやさしく先端的な科学技術をバランス良く学べるのが本学科の特色です。環境と組する総合的な視点と力を養い、興味・関心があるテーマについて探究していきます。
Point 2

フィールドワークや実習で自ら考え、解決する力が身に付く
3つの分野の学びに欠かせないのは野外調査(フィールドワーク)。都会にありながら河川や海に近い千住キャンパス、森林や渓流が近くにある東京西キャンパス、どちらもフィールドワークを行ううえで恵まれた環境です。さらに、小笠原・屋久島・奄美・知床といった世界遺産の地を存分に利用する「環境特別実習I」・「環境特別実習II」への参加も可能。実践的な学びを通じて、課題を発見・分析・解決する力を養います。
Point 3

科学的に環境問題と向き合う充実した実験設備・機器
千住キャンパスでは化学物質による環境汚染、水質改善など、化学から環境問題にアプロー チしたい学生のために、東京西キャンパスでは富士山や相模湖などの豊かな自然を利用し、大気や水、土壌などの環境評価研究を実践的に学びたい学生のために、それらの評価や分析を科学的に行うための実験設備・機器を充実させています。高度な科学技術で正確に分析・測定して得られたデータを解析・評価する能力が身に付きます。
学科長あいさつ Voice
人と自然が共生する持続型社会の発展に貢献する
実践的な人材を育成します

学科長・教授
橋本慎治
自然環境学科は自然の豊かな上野原市(東京西キャンパス)と都市部である足立区(千住キャンパス)の両方のキャンパスにあります。 現在,地球上では二酸化炭素濃度の上昇による温暖化、海洋酸性化,土地開発,気候変動,外来種による生物多様性の喪失,富栄養化やプラスチックゴミなどによる水質汚染といった様々な環境問題が起こっています。 自然環境学科はこのような環境問題に対して「生物環境分野」「環境保全分野」「環境科学分野」の3つの分野を軸に,多くのフィールドワークを通して、問題解決のために立ち向かえる人材の育成に重点を置いています。「生物環境分野」では特別実習として世界自然遺産の小笠原諸島,知床,屋久島,奄美大島での野生生物の観察をおこないます。「環境保全分野」では上野原市内の里山や河川,都内にある井の頭公園や葛西海浜公園において動植物の生態を調査し,里山・里海の生物多様性を保全するための取り組みを学ぶ野外実習をおこないます。「環境科学分野」では野外実習として緑豊かな自然に抱かれた上野原市と都市部の足立区という本学の立地条件の利点を取り込んだ大気調査、神奈川県民の水がめで上野原市からほど近い相模湖での水質調査が用意されています。 また,4年生で履修する卒業研究では各教員の専門分野を活かした研究を行うことができます。「生物環境分野」の研究室では,小笠原諸島でのイルカの生態,東京湾に生息する魚類の食性,植生の垂直分布などの研究,「環境保全分野」の研究室では,日本各地の絶滅危惧種の分布状況や,外来種が生態系に及ぼす影響といった研究を行うことができます。「環境科学分野」の研究室では,富士山での大気,東京湾やその流域での水質,プラスチックごみ問題を解決するためのバイオマスプラスチックの開発,燃料電池材料の応用が期待されるカーボンナノチューブの開発などの研究を行うことができます。 このように自然環境学科は,科学的知見と実践的アプローチを活用して,環境問題の解決に貢献できる人材の育成を行っています。環境に興味のある高校生や保護者の方は、ぜひ、オープンキャンパスにいらして下さい。自然環境学科の取り組みや学生生活などについて、学生や教員が皆さんと直接お話しできればと思います。
千住キャンパス
篠原研究室 篠原 正典 教授
動物の行動を通して、自然の奥深さにふれる

イルカは地域によって鳴き声が違ったり、海のさまざまな浮遊物で遊んだりします。なぜこのようになっているのか、研究室では動物たちの行動をしっかりと観察し、丁寧に調べる研究を行っています。調査手法は、海に潜るなど体当たり的なフィールドワークから、何千枚もの写真を比較する、遺伝子を解析するといった根気のいる作業まで幅が広く、おのずと科学的な視点が培われるとともに、動物たちや自然の複雑かつ奥深い仕組みにふれる喜びが得られます。研究対象はイルカに限らず、ウミガメから鳥類、昆虫類まで学生の興味に応えています。
Keyword
鯨類 生態 行動
橋本研究室 橋本 慎治 教授
水圏の生態を調査し、人と自然の持続的共生を探る

プランクトンは水中内の植物連鎖の始まりに位置し、有用な水産資源を得るためには不可欠な生物です。しかし、富栄養化によって増えすぎると水質の悪化を引き起こします。水生生物にとってより良い水圏環境を維持・再生するにはどうすれば良いかを明らかにするために、海、河川、湖沼、干潟で水生生物だけでなく水質や外来種の影響などの調査も行っています。研究対象はプランクトンから魚類まで学生たちの興味に応えています。野外調査を行うことにより、自ら環境問題を発見し、解決する方法を身に付けることができます。
Keyword
プランクトン 外来種 水圏環境 食物連鎖
森長研究室 森長 真一 准教授
植物の生態を知り、自然との共生を探る

植物は、光合成を行うことにより二酸化炭素を吸収し、酸素を放出しつつ、有機物を作り出します。我々人間を含めた動物が生きていくためには、このような植物の働きが欠かせません。しかしながら、近年の環境破壊や気候変動などによって、植物の生育地が奪われつつあります。そのような植物を保全し、そして未来へ残していくために、野外調査・栽培実験・遺伝子解析などのさまざまな手法を用いて日々研究を行っています。植物の多様な生態を知ることが、豊かな自然を守ることに、ひいては自然共生社会の実現につながるものと考えています。
Keyword
植物 生態 保全 共生
山際研究室 山際 清史 准教授
燃料電池材料を、環境にやさしい方法で創製する

私たちの生活を支える、目に見えない「ナノテクノロジー」。最近では、究極の低環境負荷の発電デバイスとして知られる燃料電池にも、さまざまな炭素系のナノ材料が使われています。研究室では、日本発の先端材料であるカーボンナノチューブをはじめ、生活に役立つさまざまなナノ材料を環境にやさしい原料とプロセスで作り出し、燃料電池や化学センサ材料への適用へと展開しています。ナノ材料を合成し、構造を観察し、応用に向けた性能評価を行うといった、マテリアルサイエンスの一連の研究の流れを身に付けることができます。
Keyword
燃料電池 グルコースセンサ 環境機能材料 カーボンナノチューブ
東京西キャンパス
和田研究室 和田 龍一 教授
富士山をフィールドとして新しい分析手法を開発し大気環境の変動を明らかにする

私たちの研究室では、新しい分析手法を開発し、市販の分析装置ではできない計測を行うことで、大気環境の保全に役立つ新しい知見を得ています。富士山を主なフィールドとして活動しており、富士山の山頂から山麓の森林までさまざまな高度にて観測を行っています。観測場所は同じ富士山ですが、環境がまったく異なっており、それぞれの場所で特徴的な濃度変化を示し、大変興味深いです。
Keyword
大気環境 富士山 森林生態系 分析手法の開発
渡邉研究室 渡邉 浩一郎 教授
ファイトレメディエーション―植物による環境浄化―

植物を用いて土壌や水から汚染物質を除去する環境修復技術をファイトレメディエーションといいます。ファイトレメディエーションは環境にやさしい技術で、重金属元素などを過剰に吸収して体内に高濃度に蓄積しても正常に生育する植物種を利用することにより、汚染された土壌環境を浄化し、植物生産性の向上に貢献することができます。私の研究室では、我が国の工業地帯が海岸地域に多く存在すること、汚染された土地の有効な活用をめざすことも必要なことを背景に、耐塩性植物や付加価値が高い景観植物などを主な対象にして、重金属元素の分析によりファイトレメディエーションへの適性を調べています。
Keyword
植物 環境浄化 重金属元素
下岡研究室 下岡 ゆき子 教授
野生動物の社会や行動から環境との関わりを解明

野生動物を取り巻く環境は、同じ種でも場所によって大きく異なり、季節によっても大きく変化します。ニホンザルやクモザルは、環境の変化に対して食物を変えるだけでなく、社会構造や振る舞いを変えるなどさまざまな方法で適応しています。野生動物の社会や行動の解明は、その環境への適応の多様性を研究することにつながります。学生達は霊長類に限らず、テン、カワウ、糞虫など、各々自分の興味ある野生動物を研究しています。観察中の気づきが更なる探究心の芽生えにつながり、野生動物と対峙するなかで、自ずと自然への敬意が培われているようです。
Keyword
野生動物 霊長類 行動 社会構造 音声コミュニケーション
辻本研究室 辻本 敬 准教授
環境に優しいバイオマスプラスチックをつくる

現代社会において、化学物質は欠かせない材料である一方、化石資源の枯渇や温室効果ガスの増加、プラスチックの廃棄等による環境汚染が問題となっています。そのような背景のもと、自然界の動植物から得られる有機性資源である、バイオマス資源が注目されています。これまでのプラスチックとは異なり、バイオマスを原料とするプラスチックは、再生可能な環境調和型材料です。天然油脂やでんぷんなどの安価で豊富な原材料を用いたバイオマス高分子の開発や、生分解性プラスチックに関する研究を行い、SDGsの達成に貢献することをめざしています。
Keyword
バイオマスプラスチック 生分解性材料 グリーンケミストリー
片桐研究室 片桐 浩司 准教授
水辺環境の研究を通じて環境保全の大切さを知る

国内の河川や湖沼、都市公園の池では、排水の流入や地下水汚染、管理放棄などによる水質の悪化や外来種の拡大が問題となっています。本研究室では、水草をはじめとする水辺植物を対象に、これらがどのような環境に生育しているのか、水鳥や魚類、プランクトンなど水辺に棲む生きものとどのように関わりあっているのかについて研究しています。さらに、研究で得られた成果にもとづく水辺環境の保全・再生や、教育につながるさまざまな取り組みを、他大学の研究者や行政、企業などと共同で実施しています。
Keyword
水辺環境 保全 水草 水鳥